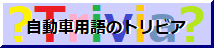
自動車に関する文書の英和/和英翻訳をしていて、面白いと思った用語や、疑問点をリストしました。
疑問点に対するご回答、記載事項の間違いに対するご指摘などございましたら、 まで、お知らせください。追加、変更したいと思います。
まで、お知らせください。追加、変更したいと思います。
インターネット上には以下のような自動車用語集や辞典があります:
Motor-Fan自動車用語集オートモ−ティブ・ジョブズ自動車業界用語辞典
ウィキペディア フリー百科事典 自動車用語一覧
グーネット自動車用語集
自動車なんでも用語集
KAWADA 自動車用語集
ミツヤ自動車 自動車用語辞典
ここから下が「自動車用語のトリビア」です
クラクション → horn *5, *6
一般に「クラクション」といえば自動車の警笛?を意味しますが、自動車業界では「ホーン」といいます。「ホーン」の語源が英語であることは明白です。「クラクション」の語源はフランスのKlaxon社の商品名からきているようです。ゼロックスやホチキスが日本語になった経緯と類似していますが、Klaxon社のホーンは現在も一部カーマニアにとっては垂涎のパーツのようです。英語のklaxonがアラームや警報音を意味するのは同じ語源であることが想像されますが、特に自動車のホーンを示すことはないようです。
オープンカー - cabriolet, convertible, roadster, spider, softtop
カブリオレ、キャブリオレ、コンバーチブル、ロードスター、スパイダーはいずれも屋根なし自動車の日本語といっても差し支えないと思いますが、同じ意味の「オープンカー」は、新聞では使用されますが、自動車雑誌では使用されないために、自動車マニアが眉を顰めて読む日本語なのではないでしょうか?英語ではsofttopともいいますが、日本語の「ソフトトップ」は自動車用語というよりはコンピュータ用語になっている感じがします。通常2頭だての四輪馬車phaetonには屋根がありませんが、自動車用語としてのphaetonはツーリングカーということになっており、現在はVWセダンのモデル名にもなっています。
交通渋滞、のろのろ運転
日本語で「交通渋滞」の類似語あるいは、同じ意味で他の表現を思いつかないので、お知らせください。また、英語には、heavy traffic, traffic jam, tail-back, tailbacks,crawling, congestion, clogged, choked, bottle-necked, full-upがありますが、他にもあったらお知らせください。しかし、英語の方が多彩に思えますが、なぜでしょうか?
遊び = play
「遊び」の訳語が「play」であることなど中学生でも知っているのですが「機械の部分と部分がぴったり結合されておらず、その間に或る程度動きうる余裕の或ること(広辞苑)」を意味する言葉が、英語と日本語で一致するなんて珍しいのではないでしょうか?それとも明治時代の直訳語だったのでしょうか?どなたかご存じないでしょうか?
『車のマニュアルのチェックを頼まれたとき、「クリアランス」か「遊び」とすべきところがみな「プレイ」となっていたのには驚きました。ドイツ語では「Spiel」ですからなるほど「play」に違いないのですが・・・』*2。 ドイツ語まで「遊び」が一致するのですね!?
半ドア = door ajar
ajarは形容詞(または副詞)なのに、なぜかajar doorとは言わないで、必ずdoor ajarというのは、ajarの語源(on char= in turning)において、aがonを意味すること、および、そのように接頭辞aで始まる形容詞は、英文法において叙述用法にのみ用いることになっているため、名詞の後にくるそうです。ただしa slightly ajar doorのようにajarが他の副詞、形容詞の修飾を受けているときは、限定修飾用法すなわち名詞の前にくることもあるそうです。*7
carburetor:キャブレター
カタカタでローマ字と英語の発音を考えれば「カーブレター」とか「カービュレター」あたりになりそうな気がしますが、carbの部分をなぜ「キャブ」と呼ぶことにしたのでしょうか?米語なまりなのでしょうか?cowをキャウというような?細かい話になりますが自動車用語としては「キャブレター」が主流であり、「キャブレタ」や「キャブレータ」は少数派のようです。
release:レリーズ
自動車以外では、カメラでもレリーズといいますね。日本では昔はレリーズといって、最近はリリースというようになってきたのでしょうか?自動車とカメラを除けば、日本語として「リリース」が一般的なのではないでしょうか?
ワッシャ、ウォッシャ=washer
英語はwasherでひとつの単語なのに、日本語では「ワッシャ」とは「座金」のこと、「ウォッシャ」とは「洗浄液」のことと、厳密にカタカナ表記と意味を区別するのはなぜでしょう?
boring:ボーリング
シリンダの内径のことは「ボア(bore)」というのに、シリンダの内側を切削することは、なぜ「ボアリング」といわないで「ボーリング」ということに決めたのでしょう?
諸元 = specification, dimension
自動車の「主要諸元」、あるいは「諸元」は通常、英語では「Specification」と書かれますが、まれに「Dimension」あるいは「Dimension and capacity」などどと書かれる場合もあります。Specificationを日本語に訳すと「諸元」または「仕様」になりますが、「仕様」という日本語は正式、公式なニュアンスが強いため、やや意味があいまいな「諸元」という言葉がカタログなどで使用されるようです。英語の「Dimemsion」は、sizeと同様、「寸法」のみを限定して示すことが多いのですがまれに、寸法以外に重量、容量、ときにはエンジン性能まで含まれることもあります。このような場合、日本語として「寸法」は不適切になり、「諸元」がよく意味を表すと考えられます。しかし、市販の和英辞典には「諸元」という日本語が掲載されていません。また、英和辞典のdimensionの訳語は「寸法、次元、広がり、面積、容積、大きさ、かさ、規模、範囲、重要性、一面、特徴、特質」などであって「諸元」という訳語は掲載されていません(注1)。
high-centered = 車の中心が高い
日本語では「車の中心が高い」といわないため、「最低地上高が高い」ので悪路走破性に優れる場合と、high-centered massまたはhigh-centered gravityすなわち「重心が高い」のでロールしやすい欠点を示す場合で表現を変える必要があります。
最低地上高 = ground clearance
自動車のタイヤを除くシャーシ下部の一番低いところ(通常はデファレンシアル・ケース下端)から地表面までの距離、間隙を日本語では最低地上高またはカタカナでロード・クリアランスという。英語でroad clearanceというのは、橋の下や、トンネルの天井から路面までの距離、間隙のこと、道路から地雷を除去すること、あるいは(軍隊の)道路通過等を意味する。road clerance timeとは軍隊の縦列が道路の特定箇所を通過するのに要する時間を意味する。最低地上高を英語ではground clearanceという。*1
エンスト = engine stall
グランプリ出版社の自動車用語辞典の「エンスト」の項には、「エンジン・ストールを略して、エンスト、あるいはエンジン・ストップを略した和製英語という二つの説がある。いずれもエンジンが停止することで、英語のstallはこれだけでエンジンが止まることを意味する」と書かれている。しかし、英文整備書ではengine stall以外に、vehicle stall, turbine stall, window motor stallなど様々な「停止」の意味で使用されているが、故障のニュアンスが含まれる。
フェイシア = fascia
米国車ではフロント・グリル周辺のことを指し、英国車ではインストルメント・パネル/ダッシュボードのことを指す。米国車ではボディ後端をリヤ・フェイシアともいい、フロント・ファイシアと区別する。
ナンバー・プレート = license plate
ボンネット = hood
エンジン・ルーム/エンジン室 = engine compartment, under the hood
助手席 = passenger seat
エンジン・ルーム/エンジン室 = engine compartment, under the hood
助手席 = passenger seat
『英語ネイティブの友人に聞いたことがあるんです。前部座席でdriver's seat,passenger seat っていった場合、当たり前のように運転席、助手席って解釈しますが、ドライバーだって乗員のひとりじゃないですか。そしたらネイティブが、「あ、そうだね。英語でも割と非論理的な用語がまかりとおっている」とビックリしていました』*4。
トランク = trunk(米) boot compartment(欧州)(昔は長靴を入れたのか?)
フェンダー = fender
これは米国語です。英国語ではwingといいます。欧州車もwingという呼称が多く使用されるようです。
フロント・ウィンドウ = windshield, wind shield
日本語では自動車の運転席前の窓を風防(wind shield)とはいわないでフロント・ウィンドウといいます。
フロント・ガラス = windscreen, wind screen
フロント・ウィンドウのガラス板自体を指す場合は、フロント・ガラスといいます。
ルーム・ミラー = rear view mirror, inside rear view mirror, interior rearview mirror
ドア・ミラー = door mirror, side-view mirror
メカニック(自動車整備工)= technician
メカニック(自動車整備工)= technician
整備書にはtechnicianと記載されることが多いのですが、mechanicということも多いそうです。*3
トレッド = track or track width
左右タイヤ接地面の中心間の距離をトレッドといい、ホイールベースとともにタイヤの配置を示す用語である。しかし、本来、トレッド(tread)とはタイヤが路面と接触する部分を意味する。日本語においてもタイヤ用語としては、タイヤが路面と接触する部分のゴム層を示し、路面の衝撃から内部のカーカスを保護するとともに、タイヤ寿命を伸ばすという役目も果たしている。タイヤ表面には各種のトレッドパターンが刻まれ、駆動力や制動力、旋回力、排水力などの向上を図る。英語では左右タイヤ接地面の中心間の距離をtrackまたはtrack widthというので、いつ頃これを日本語で「トレッド」というようになったか不明である。
ハンドル = steering wheel*3
バック = reverse
英語ではバックのことをリバースというと思っていましたが、動詞の場合はバックすることはback、back upといいます。back a vehicle; back up the vehicle;somebody backs out of a parking slot
トレーラーヘッド = tractor
トレーラー・トラックの前半部を構成し、エンジンが装着され、トレーラーを牽引する動力車両を、英語ではtractorといい、けん引される車両部分をtrailerといいます。しかし、日本のトラックメーカーでは動力車両と貨物車両を一体一組としてトレーラーという呼称で認識しているために、tractor部分のことをトレーラー・ヘッドと呼び、英文カタログでもtrailer headという単語を使用している。一部韓国でもtrailer headという英単語を使用しているのは日本に追随しているのでしょうか?農耕器具をけん引する車両は、日本語でもトラクタと言うが、一般道路を走行するけん引車両はトラクタとは言わず、トレーラーと言うのは不思議。
gas = petrol = ガソリン
米国ではガソリンのことをgasolineまたはgasといい、英国ではpetrolといいます。日本でgasというとガスのみを示しますが、米国ではガスの場合とガソリンの場合があるので文脈から判断するしかありません。
ハイオク= premium fuel, premiusm gasoline
日本語のハイオクはhigh-octane gasolineが語源です。米国ではpremium gradefuelといいます。米国某自動車会社の日本ディーラーの整備書の指定訳語は「ハイオク」ではなく、「高級燃料」となっています。これで日本人のメカニックはハイオクのことと理解しているのでしょうか?余談ですが、欧州乗用車エンジンは「ハイオク」または「ディーゼル」が主流で、日本の乗用車エンジンの主流である「レギュラー(ガソリン)」バージョンは稀です。
ガソリンスタンド = gas pump, gas station
英国ではpetrol stationです。日本の石油会社は「サービス・ステーション」という呼び方にこだわっていますが、日本語として普及していない呼称です。
アスファルト = asphalt
道路はアスファルトまたはコンクリートで舗装されますがasphaltは米国語です。英国語ではbitumenといいます。
タンクローリー
米国ではtank truckまたはtankerといい、英国ではtank lorryといいます。日本でtankerというと船舶のみを示しますが、米国では燃料を運搬するものは船舶、トラック、給油航空機のいずれもtankerといいます。日本でローリーといえば、タンクローリーのみを意味しますが英国ではトラック一般をlorryとも称します。*5
ロール・バー:roll bar
米国車ではsport barということもあります。
追越合図/パッシング:Flash-to-pass
パッシングというのは考えようによっては奇妙な日本語ではないでしょうか?
乗り付ける:pull up, haul up
英和辞書を見ると「(車、馬)を止める」と書いてあって間違いではないのですが、「止める」だったら、stopがよいのであって、pull up, haul upとかいうと「乗り付ける」ような感じがしませんか?"The Rolls pulled up on the front lawn"; "The chauffeur hauled up in front of us"
自動車用発電機
エンジン駆動プーリーから補器ベルトを介して駆動される発電機は、ダイナモ、オルタネーターまたはジェネレーターと呼ばれる。現在の自動車にはオルタネーター(alternator: 交流発電機)が設置されており、ダイナモ(dynamo: 直流発電機)は搭載されておらず、整備書やマニュアルに「ダイナモ」と書かれることはないが習慣上、今でも作業場でダイナモという人は少なくない。ジェネレーター(generator: 発電機)は直流、交流の区別がない発電機の総称であり、少数派ではあるがそのように呼ぶ人もいる。
注1:諸元/dimensionについては河川・水資源日英用語集編集委員会による無償配布の 「河川・水資源・日英用語集」にのみ「諸元」の英訳語として「dimension」が掲載されています*2。同じグループの英和版「河川・水資源・英日用語集」には掲載されていません。
以下の方々に提供いただいた情報です。お礼の意味も含めてご紹介いたします。
*1: 吉田英毅さん*2: 井上美紀さん
*3: 森川(Kazunori Morikawa)さん
*4: 佐久間祐一さん
*5: 深瀧庸平さん
*6: クセナキスさん
*7: Sakinoさん
上記お名前の記載が好ましくない場合や、ハンドル名に変更したい場合は、末尾のメールアドレスまでお知らせください。速やかに削除/変更いたします。
上記疑問点に対するご回答、記載事項の間違いに対するご指摘、他にも意外な言い回しや用語がありましたら、下記までお知らせください。できれば修正、追加したいと思います。また、類似のホームページやブログにリンクさせていただけると幸いです。
参考ホームページ・リンク先
Eメール宛先: